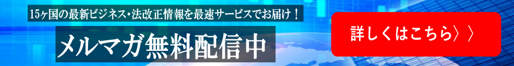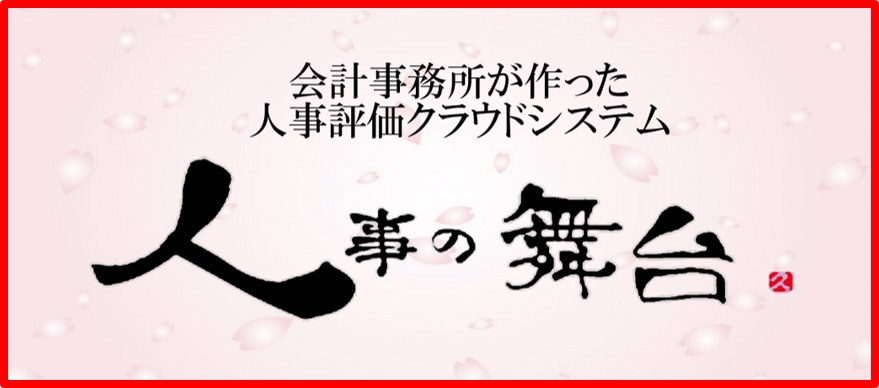みなさん、どうもこんにちは。増田です。
昨日から、日本側のインド事業部責任者である関口さんが出張でインドに来ています。
また、今週はTCFインドの全拠点の日本人駐在員がグルガオンに一堂に会し、2日間にわたってインド全体会議が行われます。当社も、インド全域で日本人6名と、インドにある会計事務所の中で最も多くの日本人を抱え、来年1月には更に2名の新たな日本人スタッフが加わります。毎年、約100社の日系企業の進出があるインドにおいて、日本人、インド人スタッフを含め更にお客様に満足していただけるようなサービスを提供していきたいと思います。
さて、今回は最近よくお問い合わせをいただくインドでの源泉所得税(特に国際間での源泉税問題)について書きたいと思います。
通常、インド国内で専門家報酬、運賃など特定の支払を行った場合、支払いの際に源泉所得税(TDS)の控除が必要となります。これは、インド国内の取引だけでなく、国際間での取引についても利息・家賃・ロイヤルティ等の支払をする場合には源泉徴収を行う必要があります。
国際間での源泉課税問題で何がやっかいかというと、取引当事国それぞれの法律が絡むという点と、あとは「租税条約」が関わってくるという点です。
仮に、日本とインドの間で源泉徴収の対象となる取引が行われた場合、
①日本→インドへの支払 ⇒ 日本の税法に基づき、インドへの支払の際に源泉徴収。
日本の税務署へ源泉税を納める。
②インド→日本への支払 ⇒ インドの税法に基づき、日本への支払の際に源泉徴収。
源泉税をインドの税務当局へ納める。
あくまで、源泉徴収を行う場合は支払を行う国側の税法に基づいて、取引内容、税率を確認のうえ徴収することになりますが、取引当事国間で「租税条約」が締結されている場合、基本的に条約が国内法よりも優先的に適用されるため、まず「租税条約」を確認する必要があります。
通常、租税条約においては「二国間取引における税の減免」が定められているため、租税条約の適用により、それぞれの国内法を適用した場合よりも税率が低くなるケースがほとんどですが、もし、租税条約の税率の方が国内法に定めらている税率より高い場合、国内法を優先して適用することができる(プリザベーション・クローズ)という決まりがあります。
日本では、海外への支払にかかる源泉徴収について、租税条約の適用を受ける場合には、所轄の税務署長に対して「租税条約に関する届出書」を提出することで減免税率の適用が受けられますが、インドでは特に税務当局に対して租税条約に関する届出を提出する必要はありません。
しかし、インドにおいては、2010年4月以降に支払われる源泉対象となる支払について、受取側がインドのPAN(納税者番号)を取得していない場合、租税条約による減免税率の適用を受けることができず、インド国内法における税率を適用する必要があります。
日本企業がインドのPANを取得した場合、毎年のインドでの税務申告を行わなければならず、また国際企業グループ間取引ということで、移転価格税制の対象取引として、Form-3CEBの提出も必要となってきます。これらの実務的な手間ももちろんですが、それ以上に問題となるのが、租税条約とインド国内税率の差分について、実質的に外国税額控除が適用できなくなる可能性がある、という事です。
どういう事かというと、日本における外国税額控除の規定上、「租税条約に定める限度税額を超える税率部分については、原則としてその還付を受けるまでは仮払金等として損金の額に算入されず、外国税額控除も適用されない」と定められているため、仮に租税条約で10%と定められている取引に対して、インドにおいて20%の源泉税が課された場合には、その差分の10%について外国税額控除の適用を受けることはできません。
もし、20%で課税をされてしまった場合には、租税条約に基づきインド税務当局に対して還付申請を行うことになりますが、実際に還付がされるかどうかは、還付申請の手続書類を全て作成した後、長ければ数年待った後でないとわからない……という現実があります。
今ではこの規定も大分知れ渡ってきましたが、インド企業との合弁のような場合で、会計面のサポートをあまり海外取引に詳しくないローカルの会計事務所が行っているような場合、この手続きを忘れてしまっている、と言うようなこともあり得ます。
日系企業については、コンプライアンスの面からも、もし対象取引がある場合には、きちんとPANを取得した上で適切に処理を行う事が望ましいかと思います。
↓クリックにご協力お願い致します↓