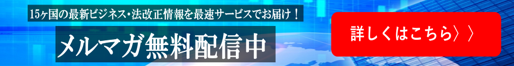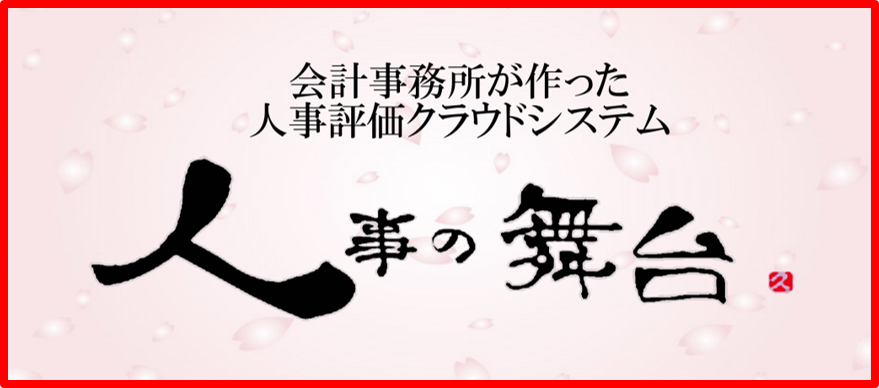お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
2013年にマレーシアでは初となる移転価格税制に対する裁判が行われ、その判決が出ました。本ブログは、その判例を解説していきたいと思います。
<関連者>
→は、グループ内の取引を表しています。
<背景>
マレーシア納税義務者であるA社は、B社(A社の親会社)の運送業務サポートをマレーシアで行う事業をしていました。その対価として、B社からコミッションを頂いていました。税務局は、これを事業所得に該当すると判断し、かつ、関連者間取引にも該当するという事で、税務調査を敢行しました。そして、その調査に基づき、この事業所得に対してペナルティーを課す権限があり、取引価格に問題があると決め、追徴課税の処置をとると決めました。A社は、これを不服とし、裁判で決着を決めることにします。
<税務局の主張>
- コミッションについて
会社の機能が変わっておらず、税務局は、比較対象企業として同業他社のコミッション収入を調べたところ、A社が受け取るコミッションは少ないということがわかり、この0.25%分コミッション収入が減少したことによる、税金を支払わないことは認められない。また、このことからもA社が独立企業間価格(Arm’s Length Principle: ALP)の原則に基づいてやっていないということが証明できる。よって、税務局は、2002年〜2005年に受け取ったコミッションに対して、追徴課税を行うことができる。
- Service Feeについて
A社がC社に支払ったService Feeに対して、独立企業間価格(Arm’s Length Principle: ALP)の原則に基づいて計算されたものではなく、また、この取引に関わる必要な書類をA社は税務局に提示できていない。よって、1998年から2005年において発生している、このService Feeの損金算入は求められない。よって、それに伴って発生する税金の調査委を行い、追徴課税することができる。
<A社の主張>
- コミッションについて
まず、税務局は、コミッションが下がった理由を会社の機能が変わっていないこと以外の理由を挙げていない。また、 コミッションというのは、保障された金額ではない。また、A社は税務局に移転価格に対する書類は提出しており、そこから見てもこの数値が勝手に決めているものではないということが理解できると思う。さらに言うと、B社は、他の第三者取引にも、コミッションを使っており、その際は我々に支払う金額より低いレートで支払っている
- Service Feeについて
税務局は、様々な理由によって、このService Feeの損金算入を認めていないことを主張している。その主な理由は、独立企業間価格(Arm’s Length Principle: ALP)の原則に基づいて算出されていない、A社に対してサービスが行われたことを示す書類や証拠もないということである。ただ、我々は税務局にサービスが行われたことを証明する書類と価格算定に使用した書類など、関連した書類は税務局にも提出し、また本際版の間も提出しているため、これは妥当な金額であると主張する。
<裁判所の見解>
A社には、本取引における価格算定に関わる資料やそれに付随した資料を提出し、独立企業間価格(Arm’s Length Principle: ALP)の原則に基づいて算出をしていることから、A社の主張を認める。よって、この2件に対する追徴課税や税金の調整を行う必要はない。
<まとめ>
本判例は、マレーシアにおいて初めてとなる移転価格を議題にした判例です。結論を言えば、しっかりと取引に関する書類を作成し、保管をしておけば税務裁判になっても負ける可能性は低くなったといえるでしょう。また、この判例において、A社が勝訴したということは非常に大きいと思います。自社においても、移転価格に関して、何か問題がありそう、ないしは出てきそうということであれば、しっかりと文書化し、保管しておくことを勧めます。
ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629