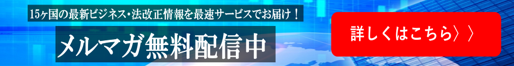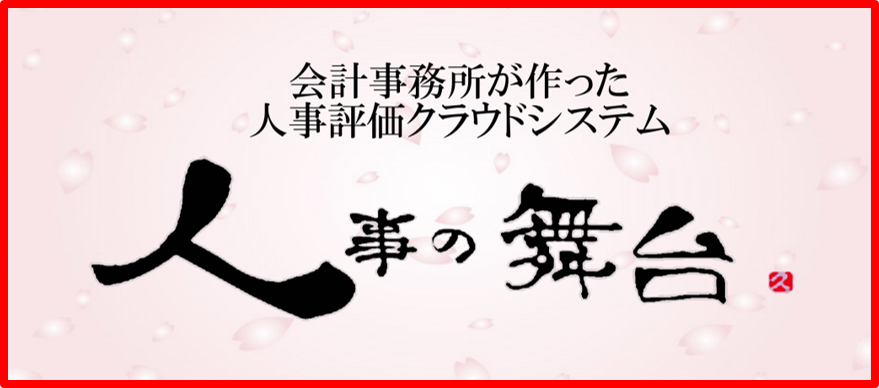<概要>
L氏はS社で勤務し、S社が雇用契約上において重大な違反を犯したことから、2014年12月15日に辞表を提出し2か月の勤務後、2015年2月14日に退職した。その後、同年2月17日、産業省長官に2月14日をもって退職した旨を報告し、退職の強要として裁判所に申し立てを行います。
このことに対してS社はL氏の退職日は、2015年2月17日ではなく辞表提出日の2014年12月15日であるとし、2015年2月17日に行った申し立ては労使関係法第20条1A項中の「退職強要の申告は60日以内に行わなければならない」という規定にそぐわないため、裁判所に本件に関する管轄権はないと主張しています。
<従業員側の主張>
L氏は2014年12月15日以前、会社が行ったリストラをきっかけとして、雇用契約を履行し続けることが困難になったことから強制的な辞任に追い込まれ、2014年12月15日に辞表を提出した。会社への辞表は、辞任日の2か月前までに提出する必要があるため、L氏は2か月間勤務したのち、2015年2月14日に退職し、同年2月17日に退職を強要されたとの旨を産業省に報告した。
労使関係法第20条1A項によると、退職を強要された申告は退職した日を起点とし60日以内に行うべきであるとしており、L氏の退職日は2015年2月14日であるため、同年2月17日に行った申告は有効であると主張した。退職日を2015年2月14日とした理由は、2014年12月15日に辞表を提出した後も2か月間勤務していること、また会社との契約は2014年12月19日をもって雇用関係は解消されていたが、契約条項では2015年2月14日まで継続しているということから2015年2月14日が退職日であるとした。
<会社側の主張>
S社は本件に関してL氏が60日以内に申し立てを行わなければならないのにもかかわらず、60日を超えてから申し立てを行ったとして、裁判所には裁判を行う権利がないと主張した。S社はL氏の解雇日は同氏が辞表を提出した2014年12月15日であると主張した。その理由としては労使関係法には会社が重大な違反を犯した場合、従業員はすぐに辞職するか、できるだけ早く辞職しなければならないと規定で定められている。また、退職強要の申告は退職を強要されたことにより退職を申し出た日を起点として60日以内に行うものと主張し、2014年12月15日が退職日であるとした。また、S社はL氏に解雇通知書を出しておらず、L氏が自ら2か月後の退職を申し出たとして本件は退職の強要には当たらないとも主張した。
<判決>
本件は退職日がいつであるのかが中心に争われました。判決としては、本件に関しては産業裁判所には管轄権がなく、L氏の請求は却下されました。
<裁判所の見解>
本件が退職の強要にあたるかどうかはまず、労使関係法第20条1Aで定める「60日の期間」の起点となる退職日を決定する必要がある。退職日についてL氏は2015年2月17日、S社は2014年12月15日とそれぞれしているが、同法においては、会社が重大な違反を犯した場合、従業員はすぐに辞職するか、できるだけ早く辞職しなければならないということが退職の条件として置かれている。L氏はS社が重大な違反を犯したことから2014年12月15日に辞表を提出した。もしも、この重大な違反が退職の原因であるとすれば、退職の強要の申告をすることのできる60日間の期間の起点は2014年12月15日かそれ以前ということになり、L氏が辞表提出後に勤務していてもその期間分、申請期日が延長するというわけではない。起点が2014年12月15日であった場合、L氏が申告した2015年2月17日は労使関係法第20条のいう60日間の期間には含まれていないため、そもそも申し立て自体が無効となっている。
<判決のポイント>
本件は退職日の決定について争われたケースとなっています。通常であれば従業員自らの意思で退職願を提出するため、退職願を提出することが退職の強要に該当することは少ないのですが、会社が重大な違反を犯した場合に、その出来事が結果として従業員を精神的に追い詰め、辞職に導いてしまった場合は退職の強要にあたる恐れがあります。
退職の強要に該当した場合、本件のように「いつが退職日の起点となるのか」ということを明らかにする必要があります。本件の労使関係法第20条1A項においては「60日の期間」というものが、従業員が退職の強要の申告を行うことのできる期間となっています。