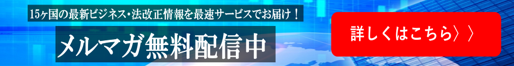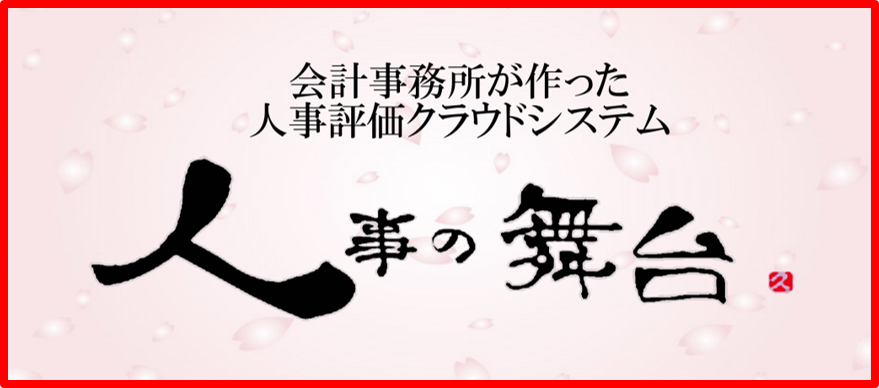お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
2013年にマレーシアで取引価格に対する税金に関する税務裁判の判決が出ましたので、今回はその判例をご紹介いたします。
〜判例:取引価格に対する税金について〜
<背景>
A社は、2000年1月〜2003年2月の間に、マレーシアで、スポーツ用品、アパレル商品やアクセサリー商品を輸入している事業を行っており、その期間分を、マレーシア関税局(KRDM)が監査したところ、本来払うべき税金を払っていないという指摘が入り、裁判でその論点を争うこととなります。
A社(親会社)が行っているビジネスは、基本的には三国間貿易と呼ばれるものであり、A社(親会社)が、商品をA社(子会社)に納品し、C社とB社はその仲介役を担っています。C社は、A社から直接支払いを受けるわけではなく、B社を経由して、その代金を受けます。A社(子会社)がこのビジネスを受けるにあたり、まず下記3点の契約書を結ぶこととなります。
- 購買契約書 A社(子会社)とC社(A 社関連会社)間
- 販売代理人及び運送代行事業契約書 A社(子会社)とB社間
- 知的財産契約書 A社(親会社)とA社(子会社)
上記の図によると、A社(親会社)に対して、3.の契約に基づいて、ロイヤルティー費用を支払っており、1.の販売契約に基づく支払いは、A社(子会社)からB社に支払い、B社からC社に支払うということになっております。このロイヤルティーについては、知的財産契約書に基づき、ライセンスを使用する商品に対する請求額の6%を支払うという契約になっています。また、契約書の条項内に、仮にロイヤルティーの支払いがなくても、本ビジネスの妨げとはならないといく記載もしておりました。
<本件の論点>
論点は、この商品購入額の中に、A社(親会社)に支払っているロイヤルティーを含んだ額ではないことが問題であり、またその購入金額分に関する税金しか払っていないことが問題であるとのこと。
<関税局による法的根拠主張>
課税価格については、関税法1967(Custom Act 1967)に基づいて計算されるものであり、併せて、課税価格に関する関税法規則1999(Custom Regulations 1999)も参考となる法律である。そして、彼らが上げている主張は、下記の通りである。
- 関税規則(Custom Regulations 1999)内の第4条1項に示されているように、課税価格は、第5条で述べる調整をした後の取引価格が適用されなければならない。
- 関税規則(Custom Regulations 1999)内の第5条1項(a)で示されているように、取引価格は、買い手が支払った、直接の支払いや間接的に支払った、いかんにかかわらず、ロイヤルティーやライセンスフィーを含んだ金額で調整をしなければならない。この法律は、マレーシアに輸出された取引に対して適用される。
よって、本件はロイヤルティーを含んだ形で取引価格を設定し、その分の税金を納める必要がある。
<上院裁判所での判決>
A社(子会社)は、マレーシアで商品に対してマレーシアに輸入された商品に対するロイヤルティーを支払っているわけではない。その理由は、契約書を別々の会社と結んでおり、ロイヤルティーは、あくまで商標などの使用権に関するものである。また、知的財産契約書の中でも、ロイヤルティーが未払いであったとしても、本ビジネスに支障はきたさないという条項を盛り込んでいることからも、このロイヤルティーが商品の輸入に関連したものではないことが理解できる。よって、契約書が別々の会社と結ばれており、この商品の輸入に関連するものではないため、本ロイヤルティーは、取引価格に含める必要はないと言える。
関税局は、これに不服を唱え、連邦裁判所へ告訴し、再度審議にかけられることとなる。
<連邦裁判所での判決>
連邦裁判所で争われたのは、以下の2点についてです。
- A社(子会社)がA社(親会社)に支払った、ロイヤルティーが、関税規則(Custom Regulations 1999)の第4条と第5条に掲げられていることに該当するのかどうか。
- 本ロイヤルティーが、この輸入商品取引に関連したものであるのかどうか。
判決としては、連邦裁判所も上院裁判所の判決を採用することとし、ここで関税局の敗訴が決定した。その際に、彼らが指針として示したのは以下の3点である。
- 本ロイヤルティーは、輸出業者(B社)に対しての支払いではない。
- 本ロイヤルティーの支払いに関する契約は、輸出業者(B社)とは別の会社(A社(親会社))と結ばれている。
上院の判決を支えたのは、やはり知的財産契約書が輸出業社(B社)とは別の会社(A社(親会社))と結ばれていたこと及び契約書内に、仮に支払われなかっとしても、この取引が中止となることはないという条項を結んでいたことです。仮に、これが同じ会社で結ばれていたとしたら、ロイヤルティーを含めた形で取引価格を決定し、納税をする必要があるという結果になったと思います。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629