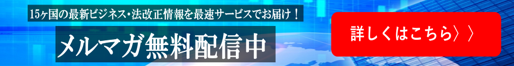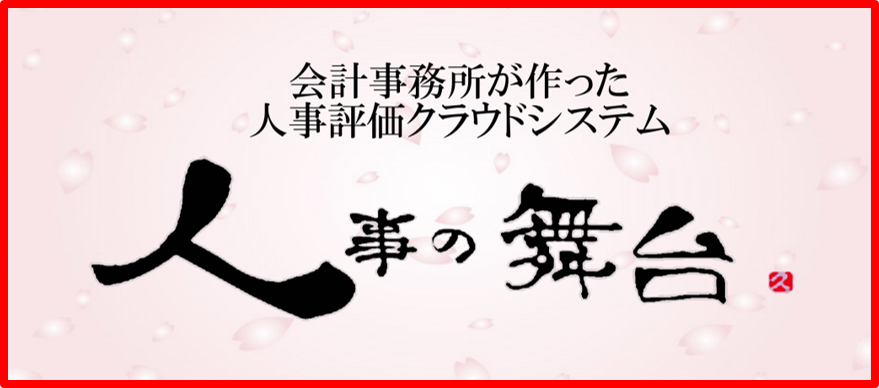判例 CASE NO: 22(14)/4-449/12
<概要>
Z氏は2008年2月25日から2010年3月23日までI社でBusiness Managerとして勤務していた。
2010年3月11日、Z氏は3月15日から同年3月19日までの間、有給休暇を取得するためにI社のE-Leaveシステムを通して有給申請を行った。しかし、確認をしたところZ氏の有給申請が未決定のままになっていたことから、Z氏はI社にこのことを報告したところ同年3月12日以後、正常に使用できるようになるとの報告を受けた。そのため、Z氏は同年3月11日にメールにて有給申請を行った。
Z氏は2010年3月15日から同年3月19日までの有給休暇を取得し、同年3月22日に仕事に戻りました。同日、Z氏の父がI社から解雇通知を受取っており、同年3月23日、I社はZ氏に対して辞職するように勧告した。
Z氏は本件に対し、解雇の本当の理由は解雇通知が出るまでの4か月間、会社と当人の関係性が良好ではなかったことが原因であり、申請が受理されていないのにも関わらず休暇を取ったということを利用して解雇に追い込んだとして、I社によって不当に罰せられたとし、I社を訴えた。
I社はZ氏の解雇に対して、会社の方針として有給休暇の申請はE-Leaveを介してのみ認められるものであり、この旨の通知はZ氏も知っていること、またZ氏が有給申請は受理されていないのにも関わらず休暇を取ったことは会社の利益を侵害するものであり、会社への背任行為であることから解雇は正当なものであると主張している。
<従業員の主張>
Z氏は2010年3月11日にE-Leaveを通じて同年3月15日から3月19日までの間で有給休暇を取る旨を申請した。有給休暇を申請した理由は同期間に、日本へ旅行に行くこととなっており、すでに航空券も購入していたのである。そして、Z氏がE-Leaveへの申請状況を確認したところ「未決定」となったままであったことから、同日中に上司にメールにて「E-Leaveに申請したがアップデートされておらず、同年3月15日から19日までの間、有給を取得する」との内容を報告した。しかし、メールでの報告のみで、直接上司に報告したわけではなかった。休暇に出ている5日間、常に連絡を取れる状態ではあったが、I社は一切連絡をすることはなかった。また、申請状況が「未決定」であったことに対して、Z氏は「未決定」の意味は「認可された」もしくは「拒否された」状態を表すものであり、完全に拒否されたものではないと主張した。
Z氏はI社が申請を承認していないのにも関わらず休暇を取得したということを理由に解雇したことに対し、このことはあくまで既成事実に過ぎず、本当の真意は両者の関係性が解雇通知が出される2010年3月22日までの間、良好ではなかったことが理由であると考え、I社による解雇は不当なものであると主張した。
<会社側の主張>
休暇申請を認めるか否かの決定権は従業員ではなく会社側にあり、会社からの承認を待たずに休暇を取得したZ氏の行為は会社の利益を侵害することに繋がり、背任行為であると主張し、Z氏の解雇は正当な行為であり認められるべきだとし、I社は本件に対し、3人の証人を立てた(COW1、COW2、COW3)。
COW1の証言によると、I社は休暇の申請に対し厳格な手続きを示しており、休暇を申請する者は5日前までに申請をすることが求められており、このことは2009年11月25日に全社員に対しメールで知らされており、Z氏はこのメールを受け取っている。
Z氏は2010年3月11日に休暇申請を行っているが、この申請は期日である5日前を過ぎているため、Z氏の申請は受理されないと証言した。そして、COW1はZ氏に対して申請期日が過ぎていることも伝えている。
また、Z氏は会社との関係性が良好ではなかったと主張しているがCOW1はこのことに関して一切認識しておらず、Z氏自身も関係性が良好ではないことを報告したことはないと証言している。
COW2は、Z氏の解雇理由について上司からの事前承認もなしに休暇を取ったことが原因であると証言した。COW2はZ氏に申請が受理されなかった理由を説明し、休暇を取るべきではないことも直接伝えていると証言している。
COW3はCOW2同様にZ氏が解雇されたのは事前承認をされていないのにも関わらず休暇を取得したことが解雇への原因と証言し、COW2が直接Z氏に対し、休暇を取得できない理由及び休暇を取るべきではない旨を伝えていることを知っていると証言している。
以上のことから、I社はZ氏が休暇を取得するべきではないということを知らされながらも休暇を取得したことに対し、会社の利益を侵害する背任行為に当たることから解雇したことは不当ではないと主張している。
<判決>
休暇を取ることに関し、Z氏が上司に直接報告することなく休暇を取得したことは紛れもない事実であり、この休暇によって会社の利益が侵害されたのもまた事実である。よって、本件に対するI社の行為は正当な解雇であり、Z氏の請求を棄却する。
<裁判所の見解>
従業員は休暇を取得する権利を有するが、雇用主の事前の承認なしで取得することに関しては抑制されるべきであるとした。また、合理的な理由によって事前に休暇を申請できなかった場合は、休暇期間中のできるだけ早い期間に雇用主にその旨を知らせるべきである。従業員の義務として、与えられた職務を雇用主によって組まれたスケジュール通りに遂行することであり、未承認の休暇を取ることによって他の従業員が当人の業務を補わなければならない状況となった場合は、会社の業務を軽視したと同義であり、これは会社への背任行為に該当する。
本件の場合、Z氏の未承認での休暇は初の行為であるが、事前に承認されていないことを告げられていたのにも関わらず休暇を取得したこと、また合理的な理由でもないことからZ氏の行為は無断欠勤であり、Z氏の行為が会社の利益に損害を与えたのは明確であった。この行動に対するI社の解雇という判断は、適当な判断とされる。
<判決のポイント>
本件は承認を得なかった有給休暇の取得という行為が解雇に該当するのかが争われたケースとなりました。本件にあたっては、Z氏の取得した休暇が合理的な理由によって取得された休暇ではないこと、またZ氏が有給申請は5日前までに申請しなければならないことを知っているにもかかわらず、有給休暇を取得したことから無断欠勤だと判断されました。
裁判所の見解であった通り、従業員には休暇を取得する権利があるため、本件のようなトラブルを避けるためにも、どのような条件を持って休暇を承認するかあらかじめ雇用契約書や就業規則に記載しておくことが重要となってきます。