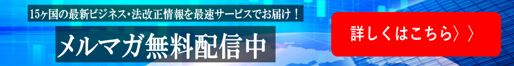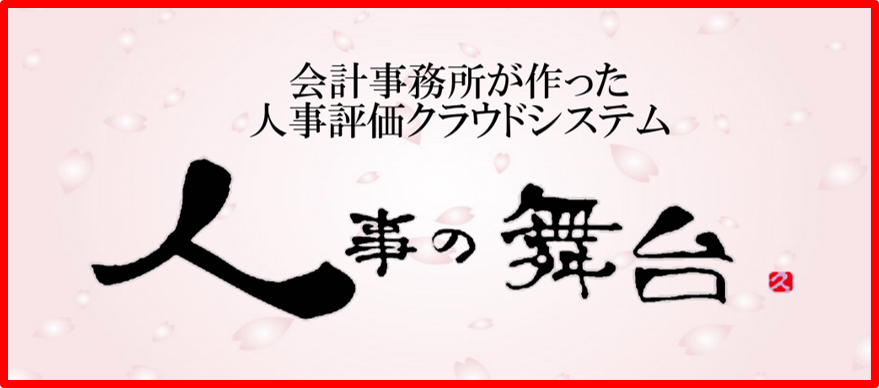いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。今回も、実際に労働裁判となった例と共に、どういうところで労働問題が起こるのかという点と、その防ぎ方について、具体的にご紹介していこうと思います。
(会社名や詳細は伏せておりますが、公に発表されている判例からご紹介しております)
今回ご紹介する例は、試用期間にてある社員を解雇したものの、「再雇用」したケースです。
<従業員側の訴え>
2012年4月から、A社はJ氏の雇用を開始。その際、6ヶ月の試用期間を設けられた。会社は2か月ごとに、それまでの評点を通知し、6ヶ月目、正社員にはできないというレターを通知した。同年10月に最終給与を付与し、解雇通知および権利放棄同意書(Waiver, Release and Quitclaim)にもサインをさせた。
しかしながら、会社は10月10日~24日までの“Retainership Agreement”という書類をJ氏に提案してきた。業務内容や責任範囲は、当初雇用された役職とほとんど変わらなかったが、給与は減っていた。
J氏は、まだ評価の途中なのだと信じ、少ない給与だったけれども、家族のためを思って同意。10月26日に再度、10月25日~11月12日の間のRetainership Agreementを提案された。しかし、内容や責任範囲は変わらないにも関わらず、給与はさらに減っていたため、今回は同意しなかった。
当初の解雇は不当なものだったとし、正式な雇用として復職されるように訴えた。
<会社側の反論>
Retainership Agreementを提案したのは、実は、別の理由があった。ちょうど試用期間が終わるタイミングで、会社のシステムがハッキングされた。J氏はその犯人の情報を知っているから、その情報と引き換えに雇用契約を結べと提案してきた。1つ目のRetainership Agreementはこの取引のために提案した。2つ目については、従業員がより長い雇用期間を求めたため提案したが、実際には班犯人の情報を持っていなかったため、給与を減らした。
よって、正当な解雇であり、取引に基づいた契約のため、再雇用ではない。
<裁判所の見解の流れ>
当初、仲裁役である全国労使関係委員会(NLRC)は、従業員側の意見を認め、会社側に損害賠償(約33万ペソ)と、J氏の復職を求めました。試用期間中の評価条件のうち、正社員になるための要件を満たしていない、という証拠がなかったとし、A社はJ氏を正社員として雇用したくなかったから、短期雇用として契約を提案したとすれば、それは不当解雇であるとしました。
しかしその後、控訴裁判所および最高裁判所では、Retainership Agreementそのものに注目されました。実はこの契約書、A社側からの署名はあるものの、J氏からの署名がなかったのです。J氏は、従業員のサインがないなんてよくあることだ、と、その契約書の有効性を訴えましたが、最高裁では、「本当に復職をしたければ署名しているはずだ」とし、無効であるとしました。結果として、損害賠償の支払いや復職という義務はなくなりました。
<ポイント>
今回の判例から学べるのは、一度雇用した人と再雇用することのリスクです。例えば有期雇用契約のつもりだったが、期間後、再度有期雇用で解雇したり、今回のように試用期間で正社員にしなかった後に(有期)雇用したりといった行動は、正社員としての雇用とみなされる可能性が非常に高いです。いくら、権利放棄同意書を書かせたと言っても、このような行為は避けた方がいいでしょう。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。人事労務含め、フィリピンでの経営に関することはいつでもご相談ください。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください