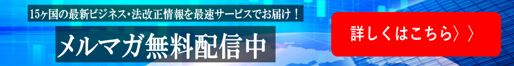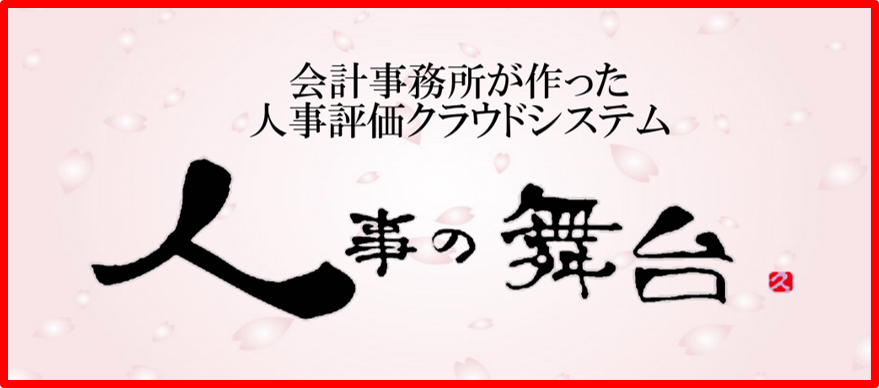いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。今回も、実際に労働裁判となった例と共に、どういうところで労働問題が起こるのかという点と、その防ぎ方について、具体的にご紹介していこうと思います。
(会社名や詳細は伏せておりますが、公に発表されている判例からご紹介しております)
今回ご紹介する例は、ある社員の退職金をめぐる労働裁判です。退職金の計算方法について、規則ではなく慣習を優先するよう訴えた社員のお話です。
<経緯>
H氏は、1980年からS社に勤務。会社代表者のアシスタントとして雇用され、2008年末の退職時には、Operating Officerという、社内で一番責任のある役職の一つである位を与えられていた。
会社は、基本給×1.5か月×勤続年数とその他手当として、約750万ペソを退職金として支払った。これに対しH氏は、労働協約(CBA)に従い、この計算は×1.5か月ではなく×2か月で計算されるべきだと訴えた。
当初、仲裁機関は、会社側の見解に同意したが、高等裁判所では、H氏の主張を受け入れ、さらに約260万ペソの支払いを会社に命じた。
しかし最高裁ではさらにこの高等裁判所の見解を取り下げ、H氏の訴えを棄却。会社側の見解が尊重された。
<H氏及び高等裁判所の見解>
CBAには、×2か月と記載されている。これまでも、同じような役職の人も×2か月でもらっており、その証人もいる。慣習に従って、H氏も×2か月で計算されるべきだ。
<最高裁判所の見解>
第一に、CBAは、労働組合の加入者のみが対象である。H氏のような管理役職の者は、労働組合にそもそも入れず、またCBAに記載の退職金も受け取ることは出来ない。
慣習的に、これまでも管理職が×2か月で計算されていたというが、その証人は12年前に退職した者。他の人もいるといっているが、実際にその人たちの名前を挙げる事も出来ていないため、「慣習的に×2か月で計算している」という証拠としては、不十分である(証人は、会社にたまたま手当を与えられたのだろう)。
もし、数年にわたる間、同じ対処がなされており、それに一貫性があるのであれば、慣習的だと認めたが、今回はそうではないため、H氏の訴えを棄却する。
<ポイント>
今回は、慣習であることの証拠が不十分だったため、規則が優先されました。しかし、もし証拠が十分にあったらどうでしょう?「数年にわたる間」「一貫性がある」対処がなされていれば、就業規則とは違う内容でも、習慣を優先させるよう、命じられる可能性があるということです。
フィリピンに限らず東南アジア諸国では、自分の所得を他の社員に教えるのは一般的です。ご注意いただきたいのは、就業規則上決められた処遇よりも良ければ、特に文句はないだろう、という扱いでは、他の社員の不平不満の種になりかねないということです。特別扱いであるのであれば、それが分かるような説明をすることが必要でしょう。
ご参考になれば幸いです。就業規則・労働協約の見直しのご検討の際は、ぜひご相談ください。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください