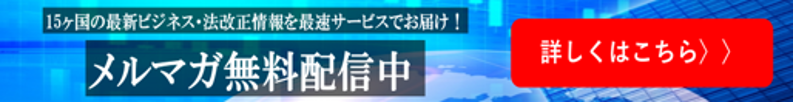去る2015年8月31日に、インドネシア企業と米国企業との訴訟において、インドネシア語で記述されていない契約書の効力が否定され、インドネシア進出外国企業に衝撃が走ったことは記憶に新しいでしょう。この判例をご存じの方も多いと思いますが、この判例の射程を正確に理解されている方は多くはありません。
1.言語法31条
インドネシア言語法には、以下の規定があります。
第1項 インドネシアの国家機関、政府、私企業、個人との合意書または契約書には、インドネシア語を用いて記載される必要がある。
第2項 前項にいう合意書または契約書に外国当事者が関係する場合には、当該外国当事者の母国語および、または英語でも記載され得る。
第1項では、契約主体がインドネシアである場合には、インドネシア語の契約書を作る必要があるようです。ところが、第2項を読むと、契約主体の一方当事者が外国籍の場合、母国語もしくは英語で記載すれば足りるというように読めます。言語法31条の素直な解釈として、契約の双方当事者がインドネシア国籍であればインドネシア語、一方当事者が外国籍であれば英語でも可というのが妥当だと言えます。
ところが、最高裁は判決理由中の判断にて、インドネシア国籍と外国籍との契約において、英語のみで記載された契約書の効力を否定しました。確かに判例はあくまで事実上の拘束力しかないと言われますが、訴訟となった時に同様の判決が下される可能性は極めて高いと言わざるを得ません。
当該判決がなされた以降、多くの外国企業は、実務上インドネシア語と英語の併記で契約書を作成しています。